ログアウト ログアウトという言葉 パソコンに対して苦手意識があると、この言葉を聞くだけで拒絶反応を起こしてしまう人もいるようです。 ログアウトとは ログインとログアウトについてまとめてみようと思ったのですが、初心者目線で素晴らしい説明をしてくれているサイトを見つけたのでそちらを紹介します。 とはサーチ さんです。 初心者目線で細かく説明してくださっています。 初心者の頃のことって忘れがちだと思うんですが、細かいところまで取り上げてくれています。 例えば、ログアウトってなに?って頃は、確かに私もログアウトしたら全部消えちゃうって思ってました。 消えたりしないよって、言ってもらえると安心しますね。 ▶ ログアウトとは何か?スマホ初心者にもわかりやすく解説 すぐログアウトする癖 今では使ったサービスは使い終わったらすぐログアウトする癖があります。 昔は、「サービスを使い終わったらログアウトしてさらにブラウザも閉じる」っていうの常識でしたよね? 最近は、時間が経てば自動的にログアウトになる場合もありますが、そうでない場合もあります。 以前、新宿のまんが喫茶で時々寝泊まりしていたのですが、パソコンを使おうとすると、前の人がログインしたままってことが何度かありました。 通常では万が一ログアウトし忘れてもスタッフの方が履歴やキャッシュを消してくれるものだと思うんですが、人間だからうっかりしちゃうこともあるんだと思います。 行きつけのカプセルホテルやサウナでタブレットをレンタルした時にも、しょっちゅう前の人がログインしたままになっていました… 一応その旨をスタッフさんに伝えるのですが、きょとんとした様子で危機感ゼロ…なぜ? 共有のデバイスでログインしたサイトは、使い終わったら必ずログアウトしましょう。 閲覧履歴やCookieも自分で削除するようにしましょう。



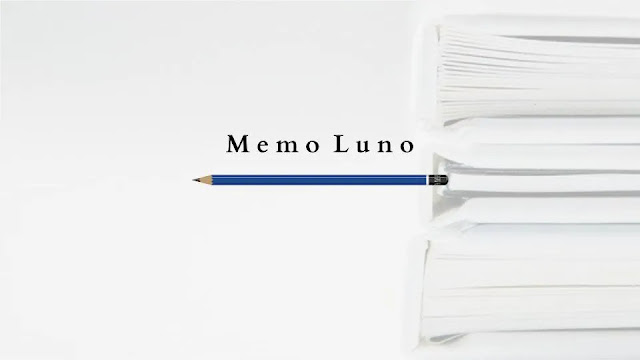
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)




